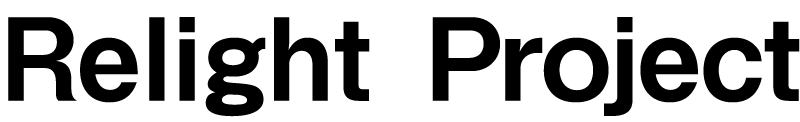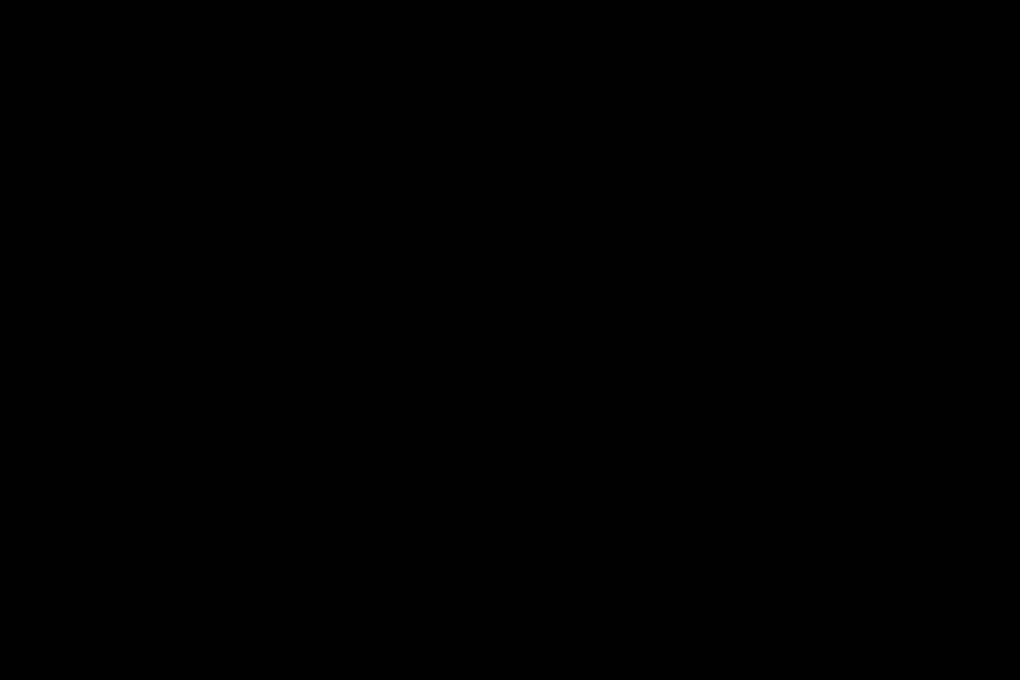開催日:2017年12月17日(日)13:00~17:00
会場:100BANCHI(東京・渋谷)
撮影:丸尾隆一
レポート執筆:南澤悠佳
Relight Symposium 2017「都市とアート/思考と実践」
第2部レポート
渋谷にある複合施設「100BANCH」で2017年12月17日に開催した「Relight Symposium 2017『都市とアート思考と実践』」。Relight Symposium 2017は、アートと都市の関わりを考察する国際シンポジウムである。
第1部では、東京、アメリカ、横浜で行われているアートプロジェクトの事例を踏まえ、「都市×アート」の現状と課題、そして今後の可能性について講演を行なった。続く第2部では、「都市におけるアートの社会的価値を考察する」をテーマにパネルディスカッションを実施。ここでは、第2部の内容をレポートする。
第1部のレポートはこちら
【登壇者プロフィール】
 宮島達男
宮島達男
現代美術家。
リライトプロジェクトの活動の中核となる作品であるパブリックアート「Counter Void」作者であり、リライトプロジェクトメンバー。また、長崎で被爆した柿の木の2世を世界の子供たちに育ててもらう活動、「時の蘇生・柿の木プロジェクト」も推進している。

帆足亜紀
アート・コーディネーター/横浜トリエンナーレ組織委員会事務局プロジェクト・マネージャー。
1994年、シティ大学(ロンドン)にて博物館・美術館運営修士号取得後、フリーになり美術のプロジェクトに携わる。2010年より横浜トリエンナーレ組織委員会事務局長補佐、2012年より同事務局長、2015年より横浜美術館国際グループ所属にて現職。通訳・翻訳も手がける。

菊池宏子
アーティスト/NPO法人インビジブル クリエイティブ・ディレクター。
ボストン大学芸術学部彫刻科卒業、タフツ大学大学院博士前期課程修了。アーティストの立場から、教育・ワークショップ開発・ボランティア育成などのプログラム開発やアートを活かした地域再生事業を国内外で展開。

綿江彰禅
一般社団法人芸術と創造 代表理事。
2006年より野村総合研究所にてコンサルティングを行い、2016年に独立。文化政策、産業政策に関するコンサルティングを専門とする。担当事業に「社会課題の解決に貢献する文化芸術活動の事例に関する調査」、「専門人材による文化団体における社会貢献活動調査」など多数。
パネルディスカッション
「都市におけるアートの社会的価値を考察する」
●状況に応じて、アートをどう使い分ける?

綿江彰禅(以下、綿江):モデレーターの綿江と申します。私は、文化政策のコンサルティングを中心に行なっています。昨今、文化芸術はそれを目的とする予算がつきづらくなっています。世の中にどう役立つのか、社会課題をどう解決していくのかが求められています。
大きな変化でいえば、2017年は文化芸術振興基本法が改正され「文化芸術基本法」ができました。そのなかで、文化芸術は観光や福祉、産業と連携しなさいということが明確に定義されました。文化芸術に関して潮目が変わる出来事と見てもいいかもしれません。
こうした状況を踏まえ、3名の方と「都市におけるアートの社会的価値を考察する」について話できればと思います。第2部から登壇される宮島さんと菊池さんに、まずは第1部の感想をお伺いしたいです。

宮島達男(以下、宮島):ジェイソン氏の基調講演を聞いて、アメリカは見えにくいものを数値化するのが得意で、日本にはそれが決定的に欠けていると感じました。
先日、リチャードセイラーさんが行動経済学でノーベル経済学賞をとりました。行動経済学は、通常の経済学が前提とする「人間は合理的に行動する」ということを否定し、人間の非合理性を取り入れた経済学です。心理学の考えを取り入れ、人間の目に見えない心の動きを数値化したものともいえます。
それをアートの世界に置き換えると、アーティストやアート関係者はアートって重要だよねと言って信じている。でも、アートに関係していない人にその重要性を説明するときに裏の数字でちゃんと実証できないもどかしさがあるんですよね。
帆足さんの講演で面白かったのは、オラファーの事例(注1)。難民問題がリアルな国と、そうではない日本ではその問題の見え方が異なる。それでも、アートを使ってその課題を扱っていく点に、同じアートでもどう使うかを考えさせられました。
私の場合、六本木に「生と死」をテーマにしたパブリックアート『Counter Void』があります。当初はパブリックアートとして存在していたものを東日本大震災後に一回消して、その後、当時の記憶を呼び起こすためにアートプロジェクト「Relight Project」で再点灯させました。アートの使い方を震災を機にスイッチした点では、オラファーの事例と似ているかと思いました。
菊池宏子(以下、菊池):私は人生の半分以上をアメリカで生活しているのですが、今日の講演を聞いていて思ったのは、英語で表現する言葉と日本語で表現する言葉で意味合いが変わってくるという点でした。
帆足さんが横浜トリエンナールでアート作品に触れるときは、「アートピース」なんですよね。それに対して、アメリカなら「アートワーク」という。「ワーク」と「ピース」では、その意味合いが大きく異なります。
私はアーティストとして活動していますが、アーティストとして働くってそもそもなんだろうと考えました。都市とアート、人と作品、街と作品……。それぞれの関係性の中で、アートがどう対応していくのか。それを話せたらいいなと思っています。
●アート作品を作るだけでなく、その後の活用も見据えた議論が必要

綿江:日本にはいたるところに裸婦像などもあったりして、パブリックアート大国ともいえると思います。パブリックアートについて考えるとき、どんな視点が必要だと、お二人は思いますか?
宮島:たとえば、ダミアン・ハーストの作品のように動物の死骸を使った作品はパブリックアートには向かないかと思います。人間は、毎日見続けるものから少なからずの心理的影響を受けることが認知科学の実験で証明されています。そのため、公の場に置くものが与える影響力を考慮して設置する必要があるでしょう。
また、私は学生の頃、新宿にあるパブリックアートを見るのが楽しみでした。でも、作品が設置された当時と今では、時代や風景が異なります。そうなると、パブリックアートの見え方も異なってくる。ある一つの役割が終わったら、撤去してもいいのではないかと最近は思い始めています。

綿江:パブリックアートは明確な目的をもたずに置くことも少なくないと思いますが、何のために置くか議論が必要ということですよね。
宮島:パブリックアートについて議論が起こったことは、日本ではほとんどないかと思います。そうした議論が起きない分、それが本当に必要かという話にもならない。市民も「そんなものあったの?」という感じで、鳩の糞の受け皿状態です。
菊池:作品を作ることが目的ではなく、メンテナンスも含めて、長期間でその意味を捉えることが必要なんだと思います。
公共の場にアート作品を置く意味を伝えることができ、地域の良さを総合的に取りまとめられるファシリテーターのような人がいるといいのかもしれません。なにか物理的なものを公共の場に置くことは、建築や都市開発と規模が違えど、同じ意味合いだと思うので、そのプロセスを見直した方がいいのかも。
綿江:帆足さんにも伺いたいのですが、横浜トリエンナーレは街中で展開しています。街の人からすれば、それらの作品はパブリックアートとの違いがわかりづらいかと思います。恒久的ではないけど、芸術祭で作品を街中に置く意味をどのように捉えていますか?

帆足:私の中では、芸術祭で置くものとパブリックアートとの違いは、期限の有無だと思っていました。でも、今のお話を聞いて、パブリックアートの役割にも期限があるという視点を知って。私のように周期的に芸術祭に関わる身からすると、パブリックアートはもっと恒久的なものであってほしいと思いました。恒久的なものと一時的なものが両方あることで、時代とともに文化を読み替えていけるのではと思います。
●アーティスト以外の人がアートに関わる意味
綿江:菊池さんがアーティストと一般の人の橋渡し的な存在としてファシリテーターが必要とおっしゃいましたが、帆足さんは横浜トリエンナーレに携わり、そういった存在についてどう感じますか?
帆足:行政のシステムはルーチンが決まっているんですよね。そのため、アーティストと行政の人の間に立つのはとても難しい部分があります。また、アート独自の言葉が行政の人には理解しづらいという現状もあります。いっそのこと、役所にアーティストが勤めていたら、共通言語を編み出して、何かが変わるのかしら?と思うこともあります。
宮島:いろんな立場の人をつないでいく、ファシリテーターやマネジャーの存在はたしかに重要だと思います。基本的に、アーティストは一般の人に説明していくスキルが弱いですから。
菊池:ただ、どういう人材が必要かは、最終的にはそのプロジェクトの目的によるかと思います。それによって、どういう組み合わせの人材、どういう仕組みが必要かを考えないと。実際、社会問題に興味関心を持っている若い世代のアーティストは増えていると思います。
また、「Relight Committee」(注2)に携わっていると、アーティストでなくても、アートを通じて社会に対して何かをしたいという人が多いと感じています。
●アートは社会課題に対してどのような効果をもたらすのか

綿江:アートの“純粋培養”ではなく、もっと多様な人を巻き込むことですよね。宮島さんの『Counter Void』は、制作当時と現在で役割が変容した一例だといえます。社会課題に対し、どういう効果や成果、影響を与えたのか。何を生み出したのかお伺いできますか?
宮島:まず『Counter Void』が消灯したことを話すと、僕が作者として消すことを決めました。東日本大震災の被災者への鎮魂と節電のためです。
それをなぜ再びつけることになったかというと、震災から3年くらい経つと、当時の記憶が薄れていることに怖さを覚えたからです。『Counter Void』を消したことは震災があったことを意識化させることだったけど、ずっと消えていることで今度は無意識化につながってしまった。もう一回つけることで、震災が起きたことを意識化できるんじゃないかと思ったんです。
帆足:再点灯と消灯を自分一人で決めるのではなく、人々に問いかけることにしたのはパブリックアートだからでしょうか?
宮島:そうです。一人で決断して実行しても、個人の作品の内部消化でしかない。アートを使って、今目の前にある問題を意識化してもらいたかった。
菊池:正直、パブリックアートを活用したことでの効果や成果は、測定結果を目で見ることができるわけではないので、なんともいえません。
今運営しているRelight Committeeは多くて10人規模ですが、再点灯に行き着くまでにさまざまな思考がありました。そうした熱量や思考を担保することが、Relight Projectにおいては重要だったと私は考えています。その活動に関わってくれた人が今日も手伝いに来てくれているのですが、彼らのアートと関わりたいという意思を感じる限り、重要性を訴え続けたいと思いますね。
宮島:一つの目に見える効果でいえば、近隣の小学校との関わりが生まれたことは、予想を上回った効果といえるかもしれません。Relight Projectに賛同してくれた教員の方が授業のカリキュラムを変更し、児童とアートと社会を考える取り組みが行われましたから。
●パブリックアートは誰のもの?

綿江:最後に質問を会場から受けたいと思います。
会場:以前、とある島で仕事をした際に、パブリックアートが写真の片隅に写っていることで、使用許可が下りなかったことがあります。著作権に関わるのかと思いますが、「パブリック」とあるからにはもっと世に開かれていてもいいのではと思いました。パブリックアートは一体誰のものなのか、アーティストはそれをどのように考えているのかをお聞きしたいです。
宮島:アーティストそれぞれなので、一概にはいえないかと思います。ただ、パブリックアートであっても持ち主がいるんですよね。行政だったり企業だったり。その人たちが著作権を気にする場合は、許可が必要になることもあるかと思います。ただ、僕個人の意見でいえば、パブリックである以上、街の風景だと思いますけど。
菊池:公の場にあるということは、世に広く使われてもらってこそ意味があるはず。その点も含めて、アーティストはパブリックアートと関わっていくことが必要だと思います。
帆足:事務的な話でいえば、契約の際に著作権をどう整理するかでしょうね。作家が生きている間は連絡を取る、意匠が変わるときは連絡を取る、など。ただ、今は写真を撮ってシェアすることが当たり前になっている現実もあるなかで、どう対応するかは悩ましいことですが、現実的に対処していくことも求められます。契約を結ぶ際は「今」に照準をあてつつ、未来のことも考え、契約事項にアップデートする余地を入れておくことも重要かもしれません。
綿江:実は、私も質問された方と同様の経験があるのですが、こうした問題もそもそもパブリックアートを置く意味を議論していないから起こり得る事態といえそうですね。企業がブランディングのために置くのか、目的はどこにあるのか。恒久的に展示されることでその意味合いが変わってくることもあるので、そうしたことは今後も考えていく必要があるといえそうです。
●シンポジウムを終えて
— NPO法人インビジブル マネージング・ディレクター・林曉甫 —
パブリックアートやアートプロジェクトの存在が都市にどのような付加価値を生み出すのかということに対する検証とその実践は、これからの都市の魅力や競争力を考える上で重要なことのように思う。特に一人ひとりがスマートフォンを所有し、撮影と共有が文化として定着しつつある中、鑑賞者という言葉の意味は既に拡張されており、彼らと共にどうアートのある状況を生成していくのかということが益々重要になってくることを感じた。
シンポジウムの中では、アメリカでのアートプロジェクトでは、事業者であるNPOなどの団体が地域経済・教育・環境・コミュニティづくりなどを通貫するものとしてアートを位置づけ、アートプロジェクトを実施する財政基盤や事業環境をデザインしているところが印象に残っている。パブリックアートやアートプロジェクトをつくり・使い続けることで、始めてアートを基点にした社会づくりができるということを認識した。リライトプロジェクトを運営するNPO法人インビジブルにとっても、今後の活動の方針を考える上で大いに学びのあるシンポジウムであった。
ーーー
注1:アーティストのオラファー・エリアソンが欧州における難民問題をきっかけに新しいコミュニティのモデルを探求するために考案したワークショップ。ヨコハマトリエンナーレ2017では、複雑なランプの組み立てを2人1組で行なった。
注2:私たち一人ひとりはアーティストだというヨーゼフ・ボイスの「社会彫刻」の理念をベースに社会彫刻家の輩出を目指す少人数制の市民大学。
(終)