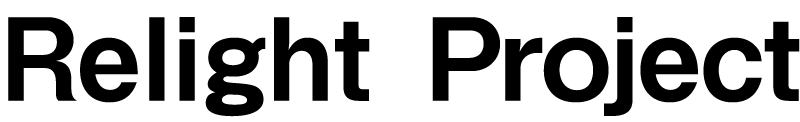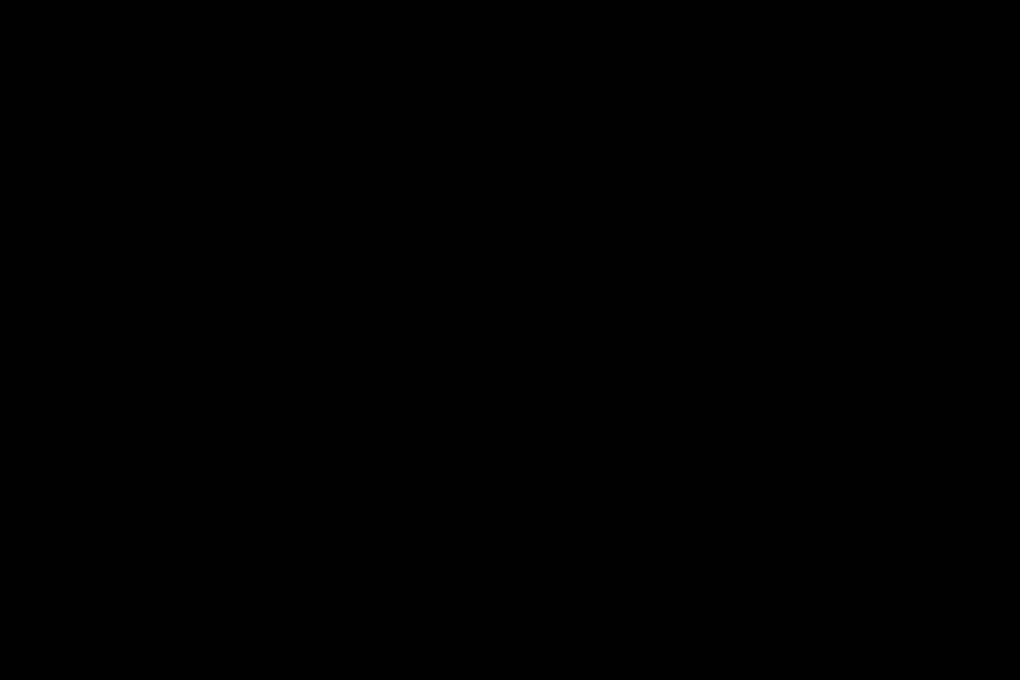六本木のけやき坂にある『Counter Void』の再点灯に向けたアートプロジェクトの「Relight Project」。Relight Session vol.2では、ライゾマティクス クリエイティブ・テクニカルディレクターの齋藤精一、ジャーナリスト、メディア・アクティビストの津田大介、アーティスト、Relight Projectメンバーの宮島達男をゲストに、「ソーシャリー・エンゲージド・アート−−行動するおとこたち」と題し、「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の意味を踏まえながら、社会に対してそれぞれの手法で働きかける実践者たちの、活動の原点やその原動力、社会との向き合い方などについてトークが行われた。1月28日に開催されたトークセッションをレポートする。
・「ソーシャリー・エンゲージド・アート」と、三者三様の活動のあり方−−Relight Session vol.2 レポート【1/3】
なにが男たちを突き動かしたのか?

菊池:齋藤さん、津田さん、宮島さんらには、今回タイトルにもあるように「なぜこの人たちは行動しつづけているんだ」というところを、なるべく聞いてみたいなと思っています。自分たちの積み重ねてきたさまざまな活動があると思いますが、何をもって現在の行動になっているのか、つながったのか。それぞれを動かしたのか。その中でも、東日本大震災は、非常に大きいと思うんですよね。
宮島:そうですね。三人がたまたま石巻とかそういうところに入っている。津田さんは、すごい早く入ってどんどんやっていたじゃないですか。
津田:そうですね、ちょうど震災が起きてから1ヵ月後の2011年4月11日には現地に行きました。
宮島:それは、突き動かすなにか、行こうと思ったきっかけみたいなものは?
津田:1995年に阪神大震災があったとき、僕は大学3年生だったんです。そのとき、なにかしたいなと思ったんだけど、何もできなかった。
宮島:一緒一緒。僕も、やっぱり阪神大震災はすごく覚えていて。だけどあの時、布団を送ったり募金をしたりはあったんだけど、実際やっぱ動けなかったんですよね。
津田:そうなんです。それがずっと心の中に引っかかっていた。その後の中越地震のときもなにもできなかった。
僕がよく一緒に活動しているジャーナリストの小寺信良さんという人がいて、彼は元テレビ番組の編集マンだったんですけど、中越地震があったときに現地に行って、現地の情報発信のボランティアをやっていたんです。それを見て「なるほど、自分の仕事で身につけたスキルを復興支援に生かせるんだな」ということを実感したんです。
ネットでの情報整理の限界、現地取材者に対する嫉妬のような感情

津田:東日本大震災の当日は、家族とはすぐにネットで連絡はついたんです。その後、ニコニコ生放送で「特番やるから司会をしてくれないか」という依頼がきた。そのとき中野にいたんですが、都内はまったく車が動かなくて、スタジオがある日本橋浜町まで4時間ぐらいかかったんです。
その4時間の間、ずっとTwitterを見ていました。Twitter上には正しい情報もあればデマも流れ始めていた。これは情報の整理が必要だなと思い、情報の整理をずっとやっていたんですね。
翌日には原発事故が起こっちゃったからこれは大変なことだなと思って、記者会見をずっと見て、新事実が判明したらTwitterに流すということをやっていた。24時間不眠不休で、ちょっと寝ても記者会見が始まったらすぐ起きるということをやっていました。
いつまでこれを続ければいいのだろうと考えたんですが、せめて原発事故が落ち着くまではやろうと思ったんです。それで2、3週間くらい経ったある時に、「あっ、これは落ち着かない」と気づいたんです。
ずっとネットの情報ばかりを伝え続えながら、現地に行って取材して記事を書いている人たちが羨ましかったんです。嫉妬に近い感情があって、事務所でずっとパソコンの前にいることにもどかしさを感じていました。
なにかできないかなと思っていた時に、ニコニコから「特番をやるので来てくれないか」って依頼が来た。それで、4月11日に初めて気仙沼に訪れ、翌日には陸前高田に行きました。
忘却しないために、行き続ける
津田:一度現場を見たら「自分がいままでパソコンで見ていたこと、伝えていたことは何だったんだ」とショックを受けました。その一方で、これから震災の報道の量は減っていくだろうから、自分ができることは現地の情報をネットを使って引き続き伝えていくことだと思った。そこから頻繁に東北を訪れるようになり、2011年の一年間で、大体25回、50日くらい行きました。
宮島:すごい行ってますね。
津田:行ってましたね。
宮島:「Relight Project」も、記憶を呼び覚まして、忘れないように忘却しないってことを心掛けているんですけど、津田さんもずっとその後もフォローし続けるじゃないですか。行き続けている。そのことを、友人の和多利浩一さんが津田さんに対して大変評価していました。
最初うわーって盛り上がった人たちは、ザーッと引いていっちゃったじゃないですか。それでも行き続けているのはすごいなって思っていて。齋藤さんもね、そういう意味ではずっと関わっていますよね。
自分の慣れ親しむ文化が、地元の人たちの力になる
齋藤:そうですね。実際に石巻に行き、「石巻2.0」に関わらせてもらっています。震災後に初めて訪れたのは3か月後くらいですね。実は、僕はニューヨークで9.11を体験しているんです。
ど真ん中のSOHO地区にいたんです。人が走って逃げてきて、さっき津田さんがおっしゃっていた匂いとかがそのままずっと残っていて。これはテレビでは全然伝わらない状態だなと思いました。
僕はマンハッタンの上の方に住んでいて、電車が動いていないので歩いて帰りました。その時に、自分も手伝おうとして印象的だったのが、「ボランティアはもう多すぎるから要らない」と言われたことなんですよ。
3.11が起きた時にも、自分が何かできないかと思いました。3か月後に行ったときにまず考えたのは、自分たちが持っているスキルで何ができるか。そこで、Twitterなどのソーシャルメディアを使って、まとめを作るなどの方法で少しづつ関わってました。
でも結局、災害の現場に行って何かできることを探したい、もう少し直接的にできないかなと思うようになるんです。けれども、実際に出来たのは炊き出しで、それが最大限の僕の出来ることだった。
でも経験もないし、得意分野ではないので、もっと効果的にできることを探そうと思って、現地を去りました。その頃に、飯田昭雄さんや建築家の西田司さんがやっている「石巻2.0」が立ち上がった。石巻では川開き祭りが7月の終わりにあるんですけど、その前に「STAND UP WEEK」というお祭りを震災終わってすぐにはじめて、マラソンも開催していたんです。
津田:フットサルやったりとか、いろいろやっていましたよね。
齋藤:普通のお祭りではヒップホップのアーティストが来てライブをするところに仙台出身のラッパーが集まったり、グラフィティのアーティストが来て、新しい楽器を使ってみたり、子どもたちにも演奏させてみたり。それを見て、僕がいつも慣れ親しんでいるような文化でも、地元の人たちに力になるようなことができるんだってことを学んだんです。
「創造力」を持った「よそ者」だから起爆できるもの
齋藤:今僕がすごく興味があるのは、それこそさっきおっしゃったみたいに押し寄せて来た人たちがいったん引いたなかで、地元で活動している人たちを持続的にサポートすること。僕がやっているのは、古山隆幸さんが始めた「イトナブ」という石巻から1000人のエンジニアを育成することを掲げた、高校生がプログラムを学ぶ道場のような場所。
最初は、古山さんからの「石巻工業高校の子たちに、ちょっとプログラミングを教えてくれませんか」という相談から始まったんですが、かなりの人が集まってきて、そこから多くの成功したプロジェクトが生まれているんですよ。
宮島:そうね、起業してるもんね。
齋藤:僕は、そこで高校生たちと石巻出身の漫画家・石ノ森章太郎の絵をプロジェクションマッピングするようなプロジェクトを一緒にやりました。彼らのなかには覚醒して起業する子もいれば、一念発起して大学に行く子も出てきた。そうした活動をサポートし続けるのが、僕がやっているプロジェクトです。
宮島:そういうのを聞くと、さっきのジャーナリズムをアクティブにしていくって動きもそうなんだけど、そこには「創造性」が絶対キーとしてある気がするんですね。つまり、創造力を持った「よそ者」が入っていかないと、起爆できなかったものがそこには見え隠れしている。
最初は炊き出しとか泥かきとか、僕も現地に行ったときには泥かきから始めたんです。だけど、それから後は創造力のキーがないとなかなかひらいていかないじゃないですか。
南三陸町の漁師との出会い、「ありがとう」からの気づき

津田:僕自身、震災をきっかけにやることも意識も大きく変わりました。創造力だけじゃなく、自分の仕事の価値ややるべきことに改めて気づかされた。
2011年5月に思想家・東浩紀が発行している『ゲンロン』という雑誌で「東北のルポを書いてくれ」と依頼され、それは大きなきっかけになりました。その依頼で、メディアという視点から東北のことを書く必要が出てきた。
いろいろなところに取材に行ったんですけど、その時はちょうど「高台移転」に興味があったんです。昔の知恵はいろんなところにあって、津波を示す地名や警告する標識が東北にはいたるところにある。
けれども、人は愚かだから忘れちゃって、そういう警告を無視して津波が来るところに家を建てちゃうんです。であれば「高台移転」は今後大事な話になるなと。興味があって調べていたら、新聞の記事でかなり早い時期――2011年の5月くらいに、高台移転のプランを市民がまとめているという活動を知りました。
それは、南三陸町の歌津地区というところで、その記事がすごく引っ掛かったので直接行ってみたんです。取材に行くときに南三陸に寄って、たまたまそこの中学校に訪れました。「高台移転のことを調べに来たんですけど」って伝えたら、こんな金髪ですから最初はすごく警戒されるわけですよ。
でも、千葉正海さんという漁師の方がとても丁寧に話をしてくれたんです。彼はその地域コミュニティのリーダーで、その人の話が興味深かったんですよね。南三陸には昔ならではのコミュニティ「講」があって、そこの「講」は、元禄時代に移り住んだ5人からはじまっていて、その子孫しか入れないそうなんです。
なんでこの地域で高台移転の話が進んだのかというと、その講が山や土地をいっぱい持っているんです。そして、こんなことが起きちゃったからコミュニティ再生のため、高台移転のための土地を講が提供して、講以外の住民も含めてみんなで移ろうという話になったんです。それで、千葉さんは先祖が「もうこれを今使えよ」って言ってくれているんだと思ったんですね。
本来は子孫しか入れないコミュニティが、こうやってオープンになっていくということに僕は感動して、それをルポで書いたんですね。それは自分でもすごく気に入っている記事なんです。
それをまとめた内容が本になったので、千葉さんに送ったんです。後日、千葉さんから電話がかかってきて「あの記事を書いてくれてありがとう」とお礼を言われたんです。「枕元に置いて、いつも寝る前に読み返している」って。驚きました。自分が書いた記事でそんなことを言われたのは初めてだったので。
大体、ルポって一回読めば終わりじゃないですか。それが毎日読んでその人の支えになっている。そういうことが文章で――しかも自分の文章で可能なんだと。それは自分にとって大きな気づきでしたね。
取材して、話を聞いてて、自分の目で見て、ルポとして伝えて広めていく。これが僕にとって、新聞部以来の大きな原体験になりました。
だれかとの関係性が原動力になる

菊池:創造するために必要なエネルギー源について、もう少しお聞かせいただけたらと思います。
津田:人との関係が生まれるってことですね。そういう関係ができると、近くに行ったら寄らなきゃな、ってなる。
宮島:人と人とのつながりですよね、きっと。齋藤さんも色んな所を見てきて、例えば創造力を持った人が、これはちょっとどうなのかなっていうのを目撃したことありました?
齋藤:いろんな理由で、協力すべきところができないのは問題だと思いましたね。こんな事態になっているのに、なんでなのかなと。
例えば、9.11のニューヨークの状況を考えると、あの時は最終的にはデモが起きて「Unite We Stand」と名付けられた、みんな立ち上がってひとつになろうという活動が起きた。ニューヨークにはプエルトリカンもジューイッシュもいる。でもあの時は、みんなが宗教も年齢も出身も関係なく一つになっていた。
もちろん、あの時は戦争が勃発するので、その戦争に対してはいろいろあったんですけど。それに対して、日本は一つになれなかったのかなとは思いましたね。
アートマーケットには食われたくない、軸足をエンゲージド・アートに
津田:宮島さんがほとんど司会のような感じになっちゃってるので、僕からちょっと伺いたくて。99年くらいに絶望しているわけじゃないですか、一回。最悪だからそこから辞めるとか他の道に行くとか、色んな道があったと思うんです。その絶望からどういう気持ちの変遷があって、色んな活動を今やられているのか、そのあたりを聞きたいです。
宮島:絶望して、完全にアートマーケットから足を洗う形もあるんですけれど、僕は20年ずっとやっていた「柿の木プロジェクト」は完全にボランティアで、自分自身が持ち出しをしてやっているようなプロジェクトなんですね。
なので、これを存続させていくためにアートマーケットも片足だけかけて、それで続けていこうって心に決めたんです。そっちはそっちで、やっぱり僕自身のコアなファンがいるし、そういう人たちに対しても「ずっと作っているよ」ってメッセージを発しなくてはいけない。
だけど、完全にそこに食われたくないってスタンスなんですよね。だからそこで、片足だけはかけているけれども、でも軸足としては「柿の木プロジェクト」とかそういうエンゲージド・アートなるものを進めていきたい。
そういうのって、パフォーマンスアートもそうなんですけど、ほとんどアートマーケットの遡上には乗らないんですね。まったくひっかかってこない。お金にはならないんだけど、そっちに軸足をしっかり置きながら、アートマーケットで売れる作品もちゃんと作っていく。そういうスタンス。
津田:齋藤さんとも近い感じがしますね。
宮島:近い。そのスタンスを取っていますね。だから、単純にケツを向けちゃうのは簡単なんだけど、いずれにしてもそういうアートマーケットとかそういうところの人たちの関心やエネルギーみたいなものがプロジェクトにも反映されていく。
津田:それでも、エンゲージド・アートに軸足を移したことによって、商業的に作る、売れる、単独で完結するアート作品の制作にいい影響を与えることってありますか?
宮島:「柿の木プロジェクト」を始めてから、本業のLEDの作品も参加型になってきた。さっきの国東もそうなんだけど、参加型のやり方を導入するようになったんですね。ですから、LEDの作品もエンゲージをするような形に徐々にシフトしてきているところなんですよね。
「飲み会」「草刈り」でアートを近づける
津田:どうやっていろんな人を巻き込んでいます? 地域アートというと、フラムさんがやっていることもそうだし、椿昇さんも瀬戸内でやっていますね。
宮島:これはもうほんと大変ですよね。さっき、津田さんが金髪で不審がられたのと一緒で、現代美術って言った瞬間に完璧にみんな引きますからね。
現代美術って言ったときに引くのに、無理やり「現代美術はこれがこうだから理解してください」ではなくて、必然的に巻き込んじゃうようにしていますね。とにかく、一番大事なのは飲み会です。
津田:飲み会ね。飲み会と、あとよく色んな人に聞くのは草刈りっていいますね。
宮島:草刈りも大事ですね。
宮島:とにかく、飲み会やって真っ先につぶれて、真っ先に歌を歌うっていう。それすると、たいていの人は心を許してくれるので。
津田:一回許していただいたら、そっから先は話が早くなりますよね。
宮島:そうなんです。そうすると、おばさんおじさんは「たっちゃん」と呼んでくれるので、そこにぐっと甘えて「じゃあこれやってもらえますかね」「いいよいいよ、やってやろうじゃないか」なんて言ってやってくれるわけですよ。
それで必然的に巻き込んでいけばその人たちは参加してくれるので、自分の作品みたいに思えてくるんですね。さっきの枕元に雑誌じゃないですけど、自分の何か血肉を分けたというか、自分の存在証明してくれるようなものに次第にアートは変わっていくんですよね。そうなったらもうしめたもので、その人たちのアートになっているんですよね。
「人」が人と地域を元気にする
津田:僕も、今の宮島さんの話はすごくわかります。パワースポット巡りのように、その場所に行って元気をもらう人がいると思うんですけど、僕にとってそれは東北がそうなんですよね。ただ、スポットじゃなくて人。だから僕はそれを「パワーピープル」と呼んでいます。
普通、取材って疲れるんですが、東北にいるパワーピープルと話すと東京に戻ってきたときに元気をもらっていることに気づくんですよね。そういうパワーピープルは、人をベースにしたツーリズムになりえると思います。
齋藤:絶対そうだと思いますよね。この前も石巻工業高校の人たちと会ったらすごく元気で、こっちが恐縮しちゃうぐらいでした(笑)。