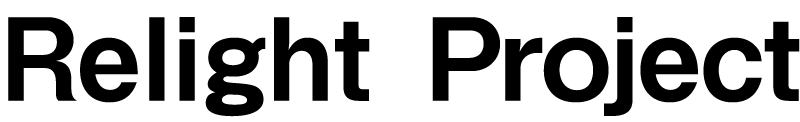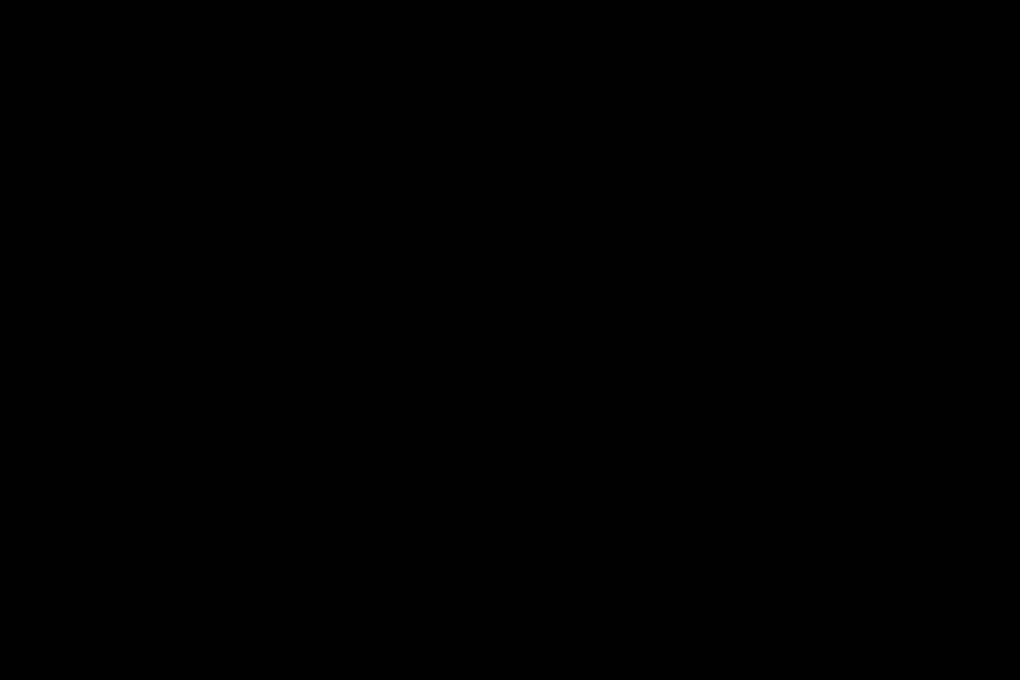六本木のけやき坂にある『Counter Void』の再点灯に向けたアートプロジェクト「Relight Project」。Relight Session vol.2では、ライゾマティクス クリエイティブ・テクニカルディレクターの齋藤精一、ジャーナリスト、メディア・アクティビストの津田大介、アーティスト、Relight Projectメンバーの宮島達男をゲストに、「ソーシャリー・エンゲージド・アート−−行動するおとこたち」と題し、「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の意味を踏まえながら、社会に対してそれぞれの手法で働きかける実践者たちの、活動の原点やその原動力、社会との向き合い方などについてトークが行われた。1月28日に開催されたトークセッションをレポートする。
「ソーシャリー・エンゲージド・アート」と三者三様の活動のあり方−−Relight Session vol.2 レポート【1/3】
・活動に突き動かされるもの、その原点とは−Relight Session vol.2 レポート【2/3】
過ちを繰り返さぬよう、見たくないものを見るためのアーカイブ

菊池:ここで、会場から集まった質問から。皆さんは、状況を風化させないためにさまざまな形で動いていらっしゃると思うのですが、それぞれの中で考える「風化をさせてはいけない理由って何ですか?」という質問が出ています。
宮島:まるで、人殺しをしちゃいけない理由は何ですか、というような質問ですね。
菊池:確かに、それくらい大きな質問ですね。補足として「風化させないこと、それを忘れない限り、被災地はずっと永遠に被災地のままなのではないでしょうか」というもう一つの質問がきています。どうお考えでしょうか。
津田:難しい質問ですね。例えば、広島って今も「被災地」ですか? 違いますよね。ただ、広島は記憶として原爆の記憶を絶対に忘れないよう、さまざまな工夫をしている。
前に中村雄二郎が言っていたことなんですけど、昔の日本人はとにかく臭いものに蓋をするのが顕著なんです。なにか不祥事があったら、その人の家ごと焼き討ちするような文化が封建時代はあったそうなんです。
かつて、東海村でJCOが臨界事故が起きました。東海村は、実はアメリカでも同じような事故を起こした町と姉妹都市で、そのアメリカの都市では事故現場がそのまま保存されて展示施設になっているそうなんです。
アメリカは、事故を起こしたらそれをちゃんと忘れないように事故現場をそのまま保存して、ちゃんと展示で見れるようにしている。当時の東海村の村上村長は、JCOもこの事故を絶対忘れてはいけないから、展示施設として現場を保存しようと主張して住民投票まで実施したんですけど、結局は経産省が主導して施設はなくしちゃったんですね。いまは小さな模型しか残っていない。
それって、臭いものに蓋をする日本人のDNAだと思うんですよね。だから、都合の悪いものでもきちんと保存するということが、これからの日本でとても大事なことなんじゃないかと思います。
事象を残すことで、地方都市のあり方を再定義できる

菊池:先日、陸前高田に視察に伺った際、国道から見える被災建築物をそのままの状態を残している住居ビルだったり、その近郊が今度公共の公園の一角になるという話を伺いました。建築的な部分も含めて、見たくないものをあれだけの規模で残すことって、どういうことなんでしょう。
齋藤:いろんな意味を持つと思うんです。阪神大震災があったときには、垂直が全部曲がってしまった建物を見ると気分が悪くなる人もいたんですが、そういうものを残すことは構造アーカイブとして価値があるともいえます。
もう一つは、さっきおっしゃったみたいに、その事象を風化させないことが大きな理由だと思ってます。僕が理解している風化させない理由の一つとして、後世にもっとも明確な形で事象を残しておくということ。今は石碑を立てなくても色んな形で残せるので、それを使ってどれだけ大変な事故だったのか、天災だったのか、もしくは今後どうやって生活をしていったほうがそれに対しての順応能力が高くなるのかを学ぶことができる。
あともう一つ、さきほどの営みの話じゃないですけど、新しい地方都市のあり方が再定義できる。結果的に、チャンスになっているような気がするんですよ。うちはWebも作っていますけど、東京にいるのが当たり前だったのが、実はもう地方ではそうじゃない意識も出始めている。
地方で活動している人たちが、打ち合わせもSkypeでできるような形をつくりあげようとしている。被災地だからということではなく、昔事故があった場所だからこそできる新しいビジネスモデルはあると思います。
よい生き方、未来を考えるためにも「忘却しちゃいけない」
宮島:齋藤さんが言ったように、僕にとって忘れないようにする本当の意味は、僕らが今生きている、生きていく上で必要なものだと思うんです。つまり、あの3.11の直後、この六本木あたりも真っ暗でみんな生き方を考えていたじゃないですか。
これからどう生きたらいいのか。エネルギーをなるべく使わないように生きたらいいな。コミュニティをしっかりさせよう。色んな生き方を考えたはずなのに、忘れちゃってもう垂れ流しじゃないですか。
もうあの事を忘れてきたがゆえに、あの時考えていたよりよい生き方みたいなこと、新しい生き方みたいなことを忘れている。それって未来にもつながっていく話で、未来の子供たちのためにどう生きるかみたいなことが完璧に忘れ去られている。
ドイツのアウシュビッツは、いまだに保存してあるじゃないですか。あれは義務教育の一環で、ドイツの子供たちが見学に行くんですよ。
津田:チェルノブイリもそうですよね。ウクライナの首都・キエフには博物館があって、みんな社会科見学で訪れている。
宮島:それを見て何になるかというと、次の自分たちの生き方をもう一度考えていくわけですよね、教育として。そういう意味で、今僕らが東京にいて、別にもう関係ないや、って言ったらそれまでなんです。自分たちのこれからの生き方みたいなものを考えていくために、それは忘却しちゃいけないんだと思います。
忘れないために残す、新しく進むためにモ二ュメント化する

津田:さっきの質問の「被災地はいつまでも被災地であり続けるんじゃないか」に対する回答にもなると思うのですが、今の宮島さんのお話も本当にそうで、アートってコミュニケーションだと思うんですよ。
例えば、僕は興味があって東北の「震災遺構」を調べていたんですね。震災遺構は、岩手・福島・宮城がそれぞれ一個づつ残すことになってて、それでアーカイブみたいな博物館を作る話になっている。けれども、たいていのものが全部壊されましたね。本当に残ったのはとても少ない。
一番有名なのは、気仙沼に打ち上げれられた第18共徳丸。それこそ、JRが作品を共徳丸で作ったりもした。
共徳丸という非常に巨大な船の前には、復興商店街があったんです。その船を見に来る人がたくさんいたけれども、周りの住民の反対もあって撤去された。その翌日から、復興商店街の売り上げは10分の1になったそうです。
震災遺構って、最初は必ず反対されるんですよ。住民にアンケートをするとどこも7割くらいは「取り壊してくれ」「残してくれ」、3割くらいは「忘れないために残してくれ」って言うけど、1、2年経つと次第に「残してくれ」って増えてきて半々くらいになる。
実際に震災遺構を撤去してしまうと、そこは野原で何もなくなる。それで、外から来た人が「ここってもともと野原だったんですよね」って言われて、逆に愕然とするみたいなことがおきる。
最初の頃は、現地を訪れた人が物見遊山で写真撮っていて、「見世物じゃないんだ」って怒っていたけども、そもそもその場所に何もなくなると人は来なくなる。そうすると、見世物でもいいから人が…なんなら写真撮る人でもいいから来てくれたほうがよかった、みたいに現地の人の気持ちも変わってくるんですよ。
そこには「俺たちは本当に忘れられちゃうんじゃないか」って恐怖がすごくあるんですよね。だから、震災遺構は忘れないという効果に加えて、モニュメントになって人を呼び寄せる効果があるわけです。
だから、結局のところは「残す」って決断をするしかないですよね。原爆ドームだって今でこそ世界遺産になったけど、1960年代くらいまではずっと壊すか残すかの議論を続けていた。でも、結局残すと決めたことが、広島をいまのような都市にしている。あれのデザインは丹下健三さんですよね。
だから、記憶を遺すという意味でアートの力はすごく重要なんです。被災地が被災地でなくなり、新しく進むために負の記憶をどう表現するのか。そこにアートをコミュニケーションに変換する創造力が求められているんだと思いますね。
ペンディングすることも大事
宮島:これからどんどんそうした創造力的なことが求められていく。
津田:壊しちゃうと戻れないじゃないですか。南三陸の防災庁舎は象徴的な遺構なんです。最後まで避難を呼び掛けて津波に流された方のお姉さんは、「そこにお参りすることで妹がまだいるって思っているから残してほしい」と話す。でも親は「壊してほしい、思い出すから」と話す。遺すかどうか、親族でも割れているんですよね。
答えが出せないから、とりあえず「10年間凍結しましょう」って決議をしたんです。すぐに結論出せないものはペンディングする。そういうこともすごく大事だなと思いますね。
菊池:今回のテーマにもなっている「ソーシャリー・エンゲージド・アート」に関して、すこしここでご質問させてください。
「エンゲージド(Engaged)」の意味に込められている“市民参加”とか“協働”に対して、みなさんは、アーティストとして、人として、どういう歩み寄りをするのかお考えいただきながら、ここで最後にお話していただきたいのが「行動するときに市民の方に期待する」こと。
要は、一緒にパートナーシップなり協働する方に対して、何を期待しながら自分たちの行動を起こしているのか。もしあればどういうことを期待して、一緒に行動をすることを考えているのか。
宮島:私が一番期待することは「自分は絵が下手だから、表現することが下手だから発言しないとか、アイデアを出さない」っていうんじゃなくて、「絵が下手で全然いいと思うし、アイデアが稚拙で全然いいので、なんかアクションを起こしたらそこからどんどん広がっていくので、自分が考えたこと思ったことをとりあえず口に出してみる、とりあえず描いてみる」っていうところから始めてほしいな。
そうするとどんどん広がるし、言ったことを他の人がそれを見て「だったらこうしたら?」みたいに、雪だるま式にそのアイデアが膨らむ。そうすると参加していて楽しいし、アートを感じることができる人は必ず創造性を持っているはず。そもそも、すべての人は創造性を持っているはず。ぜひ、そういう力を発揮してもらいたいなと思います。
「やってあげてる」でなく、「学ばせてもらっている」

津田:さっき「飲むのが大事」という話があったじゃないですか。加えて言えば、「用もないのに顔を出す」ということが大事かなと思っています。
「なんかわかんないけど、近くまで来ちゃったから寄った」みたいな。実はそういう時にこそいろんな学びがあったりするし、面白いことができたりもする。用もないのに訪れたときにこそ、なにか新しいものが生まれたりすると思うんですよね。
気仙沼でいろんな活動を行っている糸井重里さんと対談した時に、すごくハッとさせられたことがあったんです。糸井さんの事務所は、ずっと気仙沼とか震災復興のことを関わっているんですが、会社の予算としてそれを「事業開発費」にしたらしいんです。CSRではなくて、学ばせてもらいに東北に行っているんだとおっしゃっていました。
「学びは事業開発費なんだ。だからこれくらいコストがかかるんだ。でもそれはいずれちゃんと、自分たちのやることに対して戻ってくるんだ」という考え方がそこにはある。
外から関わる人間として謙虚でいることと同時に、そういう考え方が大事なんじゃないかなって思っています。
齋藤:僕は「Playable City」という、街をどう遊ぶかをテーマにしたブリストルから始まったプロジェクトを東京でやっています。最近思うのは、そうしたまちでおこなうアートプロジェクトにおいて、対象を漠然と「市民」と括っているのではないか、ということ。
でも実は、パンの焼き方を知っているパン屋さんもいれば、自動車工場に勤めている人もいる。いろんな才能を持った人がいるんですよね。だからもっとミクロに見ると、そういう人たちが自分の周りにたくさんいて、彼らと共創すると面白いことがたくさん生まれる。
この前、仙台で「地下鉄東西線」という13駅の地下鉄が開通するときに、1年半か2年くらいかけてその13駅をどう使っていくかを市民と考える企画をやっていました。
そのスクールでは、コピーライティングを学んで自分たちで広告を書けますとか、アートディレクターを呼んで、写真の撮り方を学んで、自分たちでデジタルサイネージを作れますとか、コミュニケーションの方法でYouTubeでライブするにはどうしたらいいでしょうか、というような色んなことをやっていました。
1年かけて通って関係性を築いたわけですが、、最初はみんな僕らのことも知らないし、誰かもわからない人たちと一緒に飲んで、東京から来た僕らが「こういうことをしているんだ」とわかって、僕らの熱がだんだん1年間かけて伝わっていく。それで今では、彼らだけでドライブしているんですね。
最終的には、継続するため事業化をしなくてはモチベーションを失ってしまうことがあると思うので、そこも含めて最終的には事業化する人もいるし、もしくは何か自分のやっている仕事に対してフィードバックがもらえるようなものになる集まりをつくること。その一番最初の始まりが「コミュニティ・アート」でした。
津田:齋藤さんのお話を伺っていて思ったのは、それって「イタコになる」ことなのかなと。東京に我々はいるんだけど、この時にあの人だったらこういうんじゃないかな、みたいなものを想像して動く。
そのための色々な要素を分けてもらう。これは「この人だったら多分このことについてこんな風に怒っただろうな」って思って、代わりに怒る。それを突き詰めれば、自分が行動する原動力になるんじゃないかなと。
「協働」は、難しいから達成度も高く、喜びも2倍になる
菊池:会場から、何か質問はありますか。
参加者1:なんで人を巻き込むことが大事なんですか? 自分たちだけでやらないで、人を巻き込むことで何が生まれて、何がいいんですか?
宮島:一人じゃ寂しい。一人でやれないことはない。それに、人と関わって人となにかをやっていくと、面倒くさいことも多いんですよね。だからアーティストってタイプが二つあって、自分のアトリエの中で完結して自分だけでやっている人も結構いるんですよ。
もともと僕もどちらかというとそっち側の人間だったんですけど、一度人と関わるようなプロジェクトの味を知ると、蜜の味なんですよ。
津田:難しい分、達成度が高いですよね。
宮島:そうなんです。難しいから達成度も高いけれども、喜びも二倍になります。一人で作って一人で完成して、一人でワインを傾けながら「ふふふふ」「いいね」って言っているのと、みんなで打ち上げで「わー」っていうのと、どっちが楽しいって言ったら、俺は絶対後者だよね。みんなで「わー」ってやった方が絶対楽しい。
突拍子もないアイデア、予想外がたくさん起こる楽しさ
津田:あとは、一人では時間も能力も限界がある。それを変えられるのがチームワークですよね。困難なものが困難であればあるほど、それがうまくいったりうまくいかなかったりもするんですけど、でもやっぱりうまくいったときに得られるものが大きい。
僕が南三陸の千葉さんから教えられたように、自分のことって自分ではわからないんですよ。わかっているようでわかっていないことを、チームワークはそれを教えてくれる。それは成長の機会にもなるんです。
齋藤:僕はどちらかいうと一人で作っていくタイプなんですけど、さっきおっしゃったみたいに、一言でいうと楽しいのが一つ。あと、自分で作っていると大体終わりが見えるんですよ。要は、これがこうなってこれぐらいの予算で、こうなってこう終わるんだろうなっていうのが。
ただ、人が介入すると突拍子もないアイデアを持ってきたり、「うちの実家が空き家なんでそこでギャラリーやりましょう」みたいなことが起こったりする。そこで共創すること、ともにつくることで生まれるプロセスは、予想外がたくさん起こる楽しさがそこにはあるんです。
菊池:それでは、時間となりましたのでもう一つの質問は残念ですが、ここで終わりたいと思います。今日はありがとうございます。
これで、Relight Session vol.2を終了したいと思います。ありがとうございました。