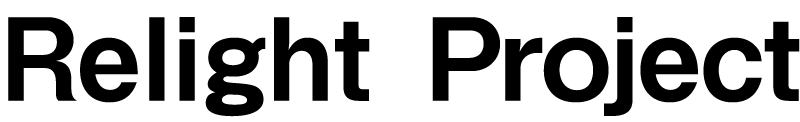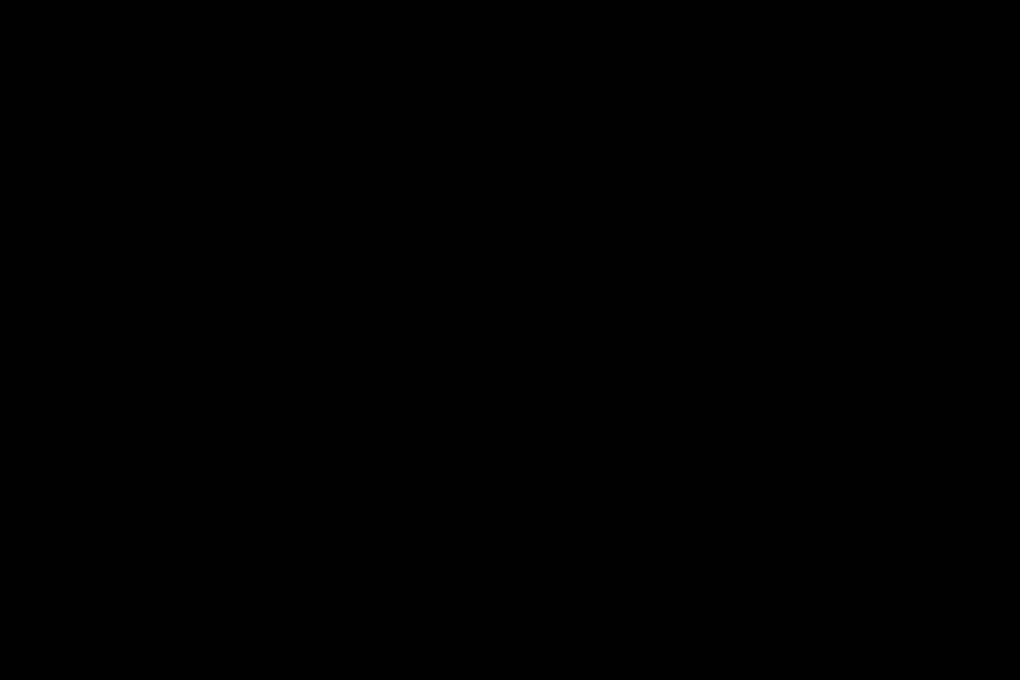六本木のけやき坂にある『Counter Void』の再点灯に向けたアートプロジェクト「Relight Project」。Relight Session vol.3では、起業家・情報学研究者のドミニク・チェンをゲストに、アーティスト、Relight Projectメンバーの宮島達男、inVisibleの菊池宏子がモデレーターに、「アート×社会ー見えないモノを想像するー」と題し、情報社会とアートの関係、アートがもつ可能性と人の行動のあり方についてトークが行われた。Relight Days3日目の3月13日に開催されたトークセッションの内容をレポートする。
・クリエイティブ・コモンズとアートの関係−Relight Session vol.3 レポート【1/3】
誰にも囚われることなく動ける美しさ

ドミニク:先程の、成仏させたいって言葉がすごく面白かったんですけども、このプロジェクトはどういう風に成仏させようとお考えなんでしょうか?
宮島:僕がどうこうしたいというよりは、Relight Committeeのメンバーなりがどうやってこの「Relight Project」自体を終わらせていくのか。それから、『Counter Void』があるこの地域が再開発されるという可能性があるんですね。その時にどういう風に終結させるのかは今後の課題で、それをやったアート・プロジェクトは未だにないんですよ。
ドミニク:なるほど。
宮島:終結のプロジェクトなんてありえないでしょ。“終わりの建築”っていうのを考えた人物がいるんですけれども、クリエイティブな世界では終わらせることは禁句なんですよ。
ドミニク:一つ思い出した事例があって、ピエール・ユイグっていうフランスのアーティストが、まさにクリエイティブ・コモンズ的なことをやってたじゃないですか。ピエール・ユイグが、アン・リーっていうアニメのキャラを秋葉原のアニメ制作会社から10万円ほどで買い取って、いわゆるコレクティブ・アートみたいな感じでいろんなアーティストと一緒に展開をして、2003年にロサンゼルスのSFMOMAで葬式展をやったんですね。アン・リーを葬るという。いろんな方が葬り方を作品にしてやって「終わらせた」、というのがまさに成仏させるという感じでした。
宮島:今回、『Counter Void』を巡ってRelight committeeメンバーがアーティストになったのは、一つには菊池さんの存在が大きかったと思います。菊池さんのアートワークはコミュニティ・デザインっていう領域をやっていて、いかにエンゲージしてエンカレッジしていくか。普通の観客をアーティストに育てていくか、そういうところをやっている人なので。どうだったんですか、今回?
菊池:あまりにも目の前にあることなので、相対的な意見はないといえばないんですけど。ただ単純に、昨日も最後の最後まで気づくと皆何かしてるんですよ、勝手に。周りの気持ちを汲み取りながら、それぞれが、自分で自分の役割をみつけて、動いているんですよ。それは私にとってもう、美しいの一言でしかなくて。
個人が、あそこまで誰にも囚われず動ける状況が頻繁におきます。周りを見渡して、自分が何をすべきか。それが単純に、掃除をするってことかもしれないし、自分の企画とは関係ないけど、仲間の企画のビラを配るっていうことかもしれないし、大変そうに見えたら、誰かの助けをすることかもしれない。
けれども、そこにはそれぞれの想像力があり、創造的な人間になっている。今目の前がそのような状況で、もう少し時間が立てば、そこまで行き着いた経緯を言語化できると思いますが、今はまだ「どうしてなんだろう?」っていう大きな問いとして残っています。
同時に宮島さんがおっしゃったように、プロジェクトの一メンバーとして、そしてコミュニティのファシリテーターとしてこれをどう形付けていくのか、どうやって継続的な活動にするのかなど多くの課題もあります。
果たしてこのプロジェクトにとって残すことの意味や、どう残すか、普遍的な、動的な活動をどのように見えるように形付けていくのか、というところですね。
アートは記述できるのか、プロセスへの興味
宮島:さっきの凹みのサービスみたいな話になるんじゃないかな。つまりね、一人一人がクリエイターに既になっているわけですよ。だとすれば、その人たちがクリエイターとして記述していく。自分が凹んだこととか面白かったことを含めて。客観的に俯瞰して、プロジェクト全体は何かを書くのは不可能。
菊池:ですよね。
宮島:だから、一人一人のアーティストが自分がどう向き合ってどう関わったかを記述して、アーカイブしていく方法しかないんじゃないかな。
菊池:はい。一つ案として出ているのは、それぞれの体験のアンソロジー化です。文章では語りきれない部分がたくさんありますが、個人の言葉でそれを語ることによって、より直接的な表現としてカタチになるのかな。アートのアーカイブみたいな型や方法論はありますよね。でも、従来の記録集的なものでなくて、個人に既存した記憶や体験、そこから派生した力(人間関係とか協働の意義とか)、それ以上のことがらをどうしたら形付けていけるか。
ドミニク:そうですよね。僕がICC(NTT インター・コミュニケーション・センター)に就職した時に最初に課せられたミッションが、いわゆるメディア・アートの作品も含む「映像のアーカイブを作る」ことだったんです。当時、ヨーロッパのZKMとかアルス・エレクトロニカ・センターとかいろいろなところと協議しながら進めていたのですが、最後までうまくいかなかった点は、結局どういう構造アートを記述するかというところで合意を形成できなかったんですよ。
それを技術に落とし込むと、「属性情報=メタ・データ」と言うんですけども、メタ・データが東京とリンツで定義がそもそも違ったら共通のアーカイブできないよね、みたいなこと。そこをいままさに頑張っているのが、先程お見せしたEuropeanaというヨーロッパ連合のアートアーカイブだったりするんです。
特にメディア・アートの場合、それまで定義したことのないような技術を使っていたりすると、そもそも共通見解が結びづらいところもあったりする。その体験を経て以来、創作のプロセスにとても興味が出てきて、先程お見せしたTypeTraceも創作のプロセス情報そのまんまなんですよね。同時にこれをやってると、ここからこぼれ落ちるものにもすごく気づかされるんです。
例えば、さきほど時間がかかった部分だけ文字が大きくなると言ったじゃないですか? だけど、それは果たして作者がこうやって頭を捻りながら、うーんってうなっていた時間なのか、コーヒー1杯淹れるのに10分間不在にしていただけなのか、そこはわからないしどういう気持ちで書いたのかはわからない。
ただ行き着くところまでいくと、先程おっしゃられたようにメンバーの人がどういう心象風景でそれと対峙したのかという情報まで、ある種SF的な話かもしれないけど、全ての感覚情報を何らかの形で記録するという発想に行き着くわけです。けれども、それが果たしてやりたいことなのかというと、そうではないのかなという気もしている。
直感や熱意は記述できない

宮島:そうだよね。だから何でも客観化できるとか、記述化できるというのは幻想なんだろうね。最近特に思うのが、アートって直感知のレベルじゃないですか。3,000人いる中で自分に合う伴侶をいかに見つけるか、みたいな。ハーバード出てるからとかシリコンバレーでいくら稼いでいるからとか、日本の美人コンテストで1位獲ってるからとか、そういうデータって関係ないじゃないですか。いくらブサイクでも自分に合って恋に落ちちゃったらもうそれっきりで、それって直感的な話なんだよね。
だから、記述できない何かがすごく大事になってきて、その直感知みたいなことを人間がちゃんと鍛えておかないと間違っちゃうんじゃないかな。3.11もそうなんだけど。つまり、あるデータに基づいて科学的知見で大丈夫って言われて想定していたものが、実は後になって想定外みたいなそういうことっていっぱいある。
むしろ、自然をコントロールしようという人間の傲慢な考え方はやっぱりダメで、どこまでいってもコントロールできない。というところから出発しないといけないのかな、って感じるところです。
菊池:同時に、記述できないところこそ、残したいっていう欲求ってありません?
宮島:まあね。
菊池:そこが一番難しいなって思っていて。アートだからこそ何かそこに大切なものがあるんじゃないかって。
ドミニク:一つ思い出しました。ちょっと前に自分で気づいて猛省したことがありまして、アート・ヒストリーとか勉強したり、いろんなものの歴史を勉強していると、その瞬間その時期、歴史オタクになっちゃうわけですね。
僕自身、非常に悪しき歴史オタク化していた時期がありまして、研究者や何か作っている友人と話をしていて、「あ、俺いいこと思いついた!」って奴がいてコンセプトを話すんです。けれども、そこに歴史オタクの僕が介入して「それって15年前にあの人が言ってるから」みたいなツッコミを入れる。すごい嫌な奴だったんですよね(笑)。幸いなことに、ある瞬間、なんてもったいないことやってるんだろうと気がつきまして。
よくエンジニアリングの世界で忌避されることが、「車輪の再発明」です。つまり「車輪」という機能を誰かが発明したとき、それを知らないで一から自分で開発したらそれは無駄ということ。機能性を合理的に追究する現場では有効な考え方なんですが、そういう言動が友人との会話のなかで自分の口から飛び出していたと思うんです。
どういうことかと言うと、15年前に誰かが同じようなことを言葉にしてしまっていたら、同じ種類のことを考えただけかもしれないけど、15年前じゃなくて2016年3月現在、その人がそのことを熱意を持って言ってることがすごく意味のあることで、それに基づいて何か新しい物を作ったとしたら、ただの模倣であったり意味のない再現ではなくて、むしろ面白いことになるんじゃないか。そういうことを思ったんですよね。
だから、歴史偏重主義っていうのも、かつての僕みたいなつまらない奴を生産してしまうという弊害もあるのかな、と。お話を聞きながら思ったのが、結局何が価値観なのかということ。シリコンバレーで成功したとかはわかりやすい指標で、そのような最大公約数的な共通の価値観が我々の社会のなかで流通しているわけですけど、それってまさに個人から発生してる欲望ではなくて、トップダウンな全体主義的な欲望の流通のさせ方ですよね。そこには産業構造とか広告技術などが関わっているわけです。
自分で何か作っている、皆で何か作っている、指示されなくても動いてることって、聞いていてそういう人材うちの会社にも欲しいなって普通に思ったんです。その状態ってどういうことかというと、極限まで自分ごとであるということなんでしょうね、その人たちには。客観的に、今これをやらないと上司に怒られるからやらないと、ってものではなくて、自分が良いと思うからやる。その状態の人間をいかに社会の中で増やしていくか。
違う知見の中で繰り広げられるストーリー

宮島:それこそがヨーゼフ・ボイスのいう「社会彫刻」なんだろうし、イノベーターですよね。このイノベーターは単に優秀なビジネスモデルを作れる人ではなくて、成功するコンテンツ作りをできる人ではなくて、さっき言った価値観なんですよ。
それが、イコール今現在お金になるならないの話ではなくて、自分の止むにやまれぬ欲求からクリエイティブな感性から欲していることなので、それは彼女彼らにとってはとてもいいことだし、社会にとってもすごくいいことですよね。
菊池:今回、すごくいろいろな形で関係がひろがっています。港区立笄小学校の江原先生は、以前トークにいらしてくださったことがきっかけで、2日間に渡るワークショップを行いました。小学4年生に対して宮島達男の『Counter Void』について勉強しましょうという入口から、Relight Projectの趣旨、そしてRelight Daysについてまで組み込みました。その江原先生の素晴らしい気持ちと行動力があり、学校が動いてくれているわけなんですよね。
ワークショップ後も、江原先生からバトンを受けるというか、それを汲み取った武田先生という音楽の先生が関わったり、校長先生が動いてくださりました。また、5日ほど前に江原先生からメールを頂きました。「菊池さん、『Relight Project』が蒔いてくれた種が花を咲かしています」という心打たれるメールが返ってくるんです。六本木アートナイトで実施した「3.11が□している」をこちらから「やってね」とは伝えていないのに、ホームルーム担当の先生たちが「これやってみよう」ということで自分たちの手元にある画用紙を使って子供たちにやってもらう。
アーティスト主体のプロジェクトの場合、従来の捉え方からするとアートやプロジェクトとなる位置付けのヒエアルキーがあると思うのですが、当プロジェクトの場合、誰かが自主的に行動すること=アートと考えるので、何を持って公式な行動かという判断はとても難しいし、多分しないと思います。
公式な場で、違う知見の中で繰り広げられているストーリーというのがすごく好きで。ある一定の層からは、これを子供たちがやった課題という扱いもあるかもしれないけれど、私からすると、それぞれが捉えた『Counter Void』の「Relight Project」に対するアートなんですよね。
今回も、Relight Days中に「子供が来たいって言うから来たんですけど、このことだったんですね」っておっしゃる親御さんがいたりして、我々のキャパを超えたところでこのアート・プロジェクトが動き出していることを少しずつ感じ始めているところです。「Relight Project」の事務局の立場として考えた時に、なんかすごいことになってるぞ、と。
このすごさって、非常に見えにくいところや直感のレベルにたくさんあるんです、これらを、どう紡ぎながら我々がストーリーを作り上げるか。例えば、技術的にそういう場面の実態が見えやすくなる方法とか、既存の技術とかあるのでしょうか?
人工知能がいかに「ジワる」か
ドミニク:インターネットでいろんなサービスが実はそういうことをやっています。例えば、ニコニコ動画は日本発の動画プラットフォームで、クリエイター奨励制度がある。いろんな人の二次創作に使われた素材を作った人に、広告収入の一部を還元するという形で対価を戻すことをやったりしてるわけですよね。
それってまさに、あるシンプルな図形だったり音楽の要素だったり動画の一要素をオープンデータ化したりして、何万人という人に使われて、その結果どれだけ多くの人に二次創作、三次創作というN次創作の物が広がっていくかは技術的には検証できる。しかしその検証の範囲はネットの世界に留まっているんですよね。
もう一つ、インターネットの計測の未熟な部分は、今はウェブサイトにしてもクリック数主義というかページビュー主義があって、例えば100万人に見られたページがある。でも、考えてみれば100万人に3秒しか見られなかったページと、100人がじっくり何回も何回も読み返すテキストがあったとしたら、時系列を挿入すると後者の方がじっくり読んだ体験をもとに何か新しいアクションを行っているに違いない。テキストをさらに読み解こうとして何かをした、というのが実際に起こっている確率が高いですよね。
そうしたことは直感ではわかっているんだけど、技術が追いついていないんですよね。だけどビジネスロジックは前者、つまり100万人に3秒の方に寄りかかってしまうので、そういうものが増えてしまう。だから「バズる」っていう言葉がネットではありますけれども、最近面白いのがバズらせるのが得意な編集者が「私、バズらせるの疲れた」って記事を書いたんですが、その記事がまたバズるみたいな循環が起こったのが面白かった(笑)。
でも「バズる」の対比として、最近希望を抱いているのが「ジワる」という言葉。「ジワジワくる」を「ジワる」と略すらしいんです。それをこないだ友人とお茶飲みながら話している時に、人工知能がいかに「ジワる」ことを理解できるか、そこに人類の希望があるような話で盛り上がったんです。
結局、時間軸が非常にショートスパンでしかいろんな物事や価値観含めて設計できていない。そこは僕も全然ペシミスティックではなくて、もっと技術頑張ろうよとか、もっと技能や設計の話をしようよってことだけ。「ジワる」って言葉に全て回収するのもどうかと思うんですが、より正確にいえば中長期的な時間尺度のなかで価値観を計測して評価することができるようになると思います。
だれのための、だれにむけた発信なのか

宮島:僕は年寄りなのでよくわからないんだけど、「『いいね』っていう共感を何万通もらったからって一体何になるの?」と思うんですよ。いいじゃない別に。自分が価値を持って作りたいと思ったもの、発信したいと思ったものを発信すればいいのであって。そうではなく、共感をもらうためのページを作るでしょ? 共感をもらうためのワードを紡ぎ出すでしょ? それってどうなのかなと思うんですよね。
一方で、ビジネスモデルとして、そういう共感をもらうためのワードを使ったり見てもらってナンボっていう世界ももちろんあるんですよ。それはそれとしていいんだけど、それが全てではないということを僕らは認識しておかないといけないよね。
菊池:言い方を変えると、個人のエンパワーメントのパワーってすごく高いわけじゃないですか。物は使いようじゃないですが、そこをきちっと使えば何かすごいことが起きる可能性に満ちあふれている。
宮島:そうなんですよ。僕は年寄りなんで、その感覚の堀が超えられないところがあって。会社の若いスタッフにも、おじさんは勘弁してくださいって言われているので。すごくわかるんですけどね、共感を得た時の喜びって。
菊池:私がわからないのは、個人と不特定多数とのつながりに今ひとつ腹に落ちていないところがある。例えば、なんで自分のパジャマ姿を見せたいのか、その欲求がわからない。
宮島:そうそう。JK(女子高生)がブチュっとキスするところを見せるとか、パンツを見せるとか、こんなのをやって「いいね」を押されて嬉しいか、と思うんだよね。
ドミニク:解説を入れると、それは「ミックスチャンネル」という非常に成功しているサービスで起きていることですね。動画のコミュニティで、女子高生、女子中学生の子たちがたくさん動画を投稿しているんです。そのなかに、カップル動画というのがありまして、カップル同士でキスしているところをパブリックな動画としてバンバン出す。
僕もそれが不思議でいろいろ調査してモチベーションは何なのかを調べたところ、彼氏が浮気をしないために公開しておくらしいんですよ。「いいね」をもらうためじゃなくて。既成事実化しちゃう。
宮島:さっきの成仏の話じゃないけれども、それって別れた時に脅しに使われるでしょう?
ドミニク:そうです。「リベンジポルノ」につながるという問題が指摘されてますね。
宮島:やばいよ。
ドミニク:単純に、人生経験足りないからそこまで思い至らないってことなんですよね。だからリベンジポルノの話は世界中で問題になっています。アメリカでも問題になっていますし、それが原因で自殺しちゃう人も出てきている。そういういろいろな摩擦が宮島さんだけじゃなくて我々の中で起こっているんです。
リアルタイムでJK、JC(女子中学生)たちもそういう問題と向き合っているんですよね。そういうことをやった結果、どうなるかということが理解できていないケースが多い。浮気して欲しくないから使えるじゃんってアップした結果、後々別れた時に恐喝されるとか、そこまでシミュレーションできていない。
インターネットってわかっていないことだらけなんですよね。こないだ家族旅行でシンガポールに行きまして、僕には4歳の子供がいるので某遊園地に行ったんですね。シンガポールはすごく面白い国で、アジアのハブなのでいろいろな人種の人、インド人もいればマレー人、中国人、韓国人、日本人、白人もたくさんいて、それが行列を作っているんです。そこで二つ面白い光景に出くわしたんです。
ひとつは4人家族で、お父さん、お母さん、弟、お姉さんが行列の中じっと自分のスマホをいじっている。何しているんだろうと見たら、それぞれが別々のニュースアプリやSNSを会話せずに読み込んでいるんですね。これはあまり良い光景ではないな、と。
もうひとつがかなり衝撃的で、たぶんインド人のご家族で、お父さん、お母さん、息子がいてて、息子は8歳くらいでお母さんは若くてすごく綺麗な感じ。そのお母さんが、行列の中ずっと自撮り棒で自撮りしているんですね。それをInstagramにバンバンアップしていて。息子がやめてよって目でお母さんを見ていて、お母さんが「君も映る?」ってやった途端、息子がバーン!ってお母さんの自撮り棒ごとはたき落として、騒然となりました(笑)。息子くんは、お母さんがずっとInstagramの自撮りばっかりしているのがすごく嫌だったんでしょうね(笑)。
幸いうちの家庭はそういうことはないのですが、その時に思ったのが、価値観はどんどん変わっていくなと。どんどん是正されていったり修正されていったりするんだろうな。その息子は、自撮りばっかりしているお母さんは嫌だという表明をパブリックにしているんですよね。でも、情報技術がもたらしているものというのは、こういうことの積み重ねだと思うんですよね。
だから、人間のくだらなさを助長してしまう部分もあれば、素晴らしいことも起こっているのがインターネットの実情。だから僕はTwitterもすごく好きだけど憎いところもあるし、Facebookもそのおかげで幸せな体験をすることもあるし、同時に良くないこともしている。
たとえば、一定のユーザーのタイムラインのアルゴリズムを、事前承諾無しにネガティブなものだけを並べる心理実験を裏でやっていることが表面化して、大問題になったことは有名です。そういう側面とポジティブな効果の両方を包括的に検証していかないと、これは邪悪だ、これは素晴らしいっていう二元論になっちゃうと議論が進まないんですよね。
評価基軸の一元化が、アートの神話化を進めている

宮島:いわゆる過渡期なんだよね。だって僕が学生時代の1980年代は、まだWindows95も出ていなかった頃で、テキストを書くのも研究室の和文タイプライターってでっかいやつをガッチャンガッチャンやりながらテキストを作っていたので、そこからすると隔世の感がするんですよね。
ドミニク:僕も10歳くらいの時に初めてメールが家にやってきて、遠くにいる友だちに送信したときに感動したんです。だけど、やっていることの本質は今も昔も変わっていないような気がしていて。量が圧倒的に変わったので、打たなくていいメールを打たされてるし、返さなくていいメッセージを返してる。
宮島:圧倒的に時間は取られていますよね。これだけテクノロジーとか情報系が発達しているのに、変わらないことはなんだろうな。ますますアートの神話性みたいなものが、神秘化されるということが強化されているような気がしてならないんだよね。
ドミニク:それは何でなんでしょうね?
宮島:ポピュリズムって話でしょう。さっき言った、良い面の共感をどれだけ得るかみたいなところに走っちゃうので、わかりやすいワンワードで撃退する。そういうところを目指すわけじゃない。そうしたら、皆そこに食いつくわけだから。
アートマーケットの評価だって、昔はいろんな評価軸があったんですよ。例えば、バーゼルのアートフェアがあって、でも一方で国際展という基軸があって、それが全然違う評価をされるアーティストもいたんですよ。両方存在できたんだけど、今やアート・バーゼルはヴェニス・ビエンナーレと完璧にリンクしちゃうようになったんですよ。
そうすると、ヴェニス・ビエンナーレに出るからアート・バーゼルにちゃんとフューチャーされる。いやむしろ逆にアート・バーゼルで売りたいがためにヴェニス・ビエンナーレにちゃんとフューチャーされるみたいな現象が起こってきているんです。
ドミニク:エレベーター方式というか。
宮島:そういうことです。だから、評価基軸がすごく一元化している。マーケットベースになってきているんです。わかりやすいから。マーケットで100万ドルついたって言えば、それはアーティストランクの1位になるわけだから。アーティストランクの1位というのは全ての人が見ますからね。
ドミニク:その傾向というのは年々強まってる?
宮島:強まっているような気がしますよね。だからアートマーケットに乗らない、吹っ飛ばされちゃうようなこういうプロジェクトは、もう全然箸にも棒にも引っかからないですよ。
菊池:個人的にはそうは思わなくて。逆にそういう市場はでき始めている気がするんですよ。市場というか、動きですよね。まだ耕している真っ最中のような。「ソーシャルリー・エンゲージド・アート」といった文脈は、まさにここ20年くらいである意味すごく社会の中に足を踏み入れながら、何かもうアート・ヒストリーじゃない文脈の所でも役割があるんじゃないかという動き。
宮島:いわゆる言語的なベースでアートを見るか、専門家の間で話題になっているか、そういう話。
菊池:そうですね。もしかしたらアート・バーゼルでは語られない部分の語りはあって。それは、アートという言葉の解釈がすごく広がった分、情報の伝わり方もすごく多様化した。ただ、そこを知らないと知らないで終わっちゃうんですよ。
宮島:マイナーレーベルの独立系展覧会みたいなものがあるんですよ。インディペンデントな。誰も知らないんですけど、そういう場所ではここらへんのアートはすごくフューチャーされている。
ドミニク:でも、本当に誰も知らないのか、1万人しか知らないコミュニティが出てきているのかですよね。
宮島:まあ少ないですよね、多分。
菊池:知る、知らないってどの立ち位置に立っているかにもよるじゃないですか。どのコンテクストで何を知っているのか。人とのつながりも含めて。そこの間に流れてくる情報とあまりにも遠すぎることで、流れてこない情報は非常に解釈がしづらいと思う。
宮島さんはメイン・ストリームまで片足を突っ込んでいるじゃないですか? その中で感じることと、そこの景色から見る景色ってすごく離れているんだろうなっていうのは、なんとなくわかるんですね。
技術で人と情報をドンピシャにつなげられるのか
ドミニク:マーケティング的なバズワードが主流メディアを流れていて、ニュースサイトを眺めていてもそういうところで引っ掛けてもらわないと、マスにはリーチできない。
けれども、もう一つ情報技術が夢見ているものがあって、それは「パーソナライゼーション」なんですよ。ランキング情報の強さって、100年どころか言語が発生して以来変わっていないわけですよね。人間ってランキングが大好きなんですよね。何が1番で何が2番か。
それを情報として集計して出す技術はすごく成熟しているし、それが多くの人間にウケるのもわかりきっている話なんです。だからこそ、優秀なエンジニアの多くが夢見ている実装したいものの一つが、ランキングという惰性に陥らないパーソナライゼーション。
つまり宮島さんがTwitterを開いたら、誰をフォローしているとか誰にフォローされているかとかではなくて、現在の宮島さんの関心のど真ん中を情報技術がわかってくれて、それにもとづいて宮島さんにだけ知られるべき情報が入ってくる。そこにはマーケティング的なバズ性とか、人気性みたいなことは上手に捨象されたり加味されていて、マイナーな情報でも知るべくして知られるというもの。
ただこれは、人間側の意識の問題もあってまだうまくいってないんですね。それがうまくいってる領域はいくつかあります。例えば「Netflix」という映画配信事業がアメリカで今5000万ユーザーくらいいます。これはある映画を観終わった時に、それを観て次に評価が高かった映画がポンと出てくる。これが映画だとうまくマッチするんです。その理由としては、映画の本数が比較的少ないからということがあると思います。
これが社会全体、インディペンデントなアート情報とかを含めると、膨大な情報のなかから「これ今のあなたにドンピシャでしょ」という風に提示するのが技術としてもまだ精度が足りない。あと、それを出された側としても、いわゆるランキング情報的な色気を感じないので、スルーしてしまったり、面白みを感じずらい。
だから、我々がランキング情報というある種の麻薬物質の中毒みたいになっていて、「これは本当に美味しいですよ」って美味しいオーガニックな食べ物を出されても、見たことないという理由で回避してしまう側面があるのかもしれない。
そこをなんとかして、みんなが知ってるわけではないけれど、自分はこれを知っておくべきだということを知られるようになったら、いわゆる今話していたようなマーケティングに全て回収されるようなことが発展的に解消できるんじゃないかな。
インターネットの確率性、現実にしかない未知との遭遇
宮島:でもちょっとつまんないような気もしますよね。全く出会ったこともないような人と出会って、「こいつなんだ?!」って思うような人に出会った時に、自分の何かをひらいていくようなことは多々あるじゃないですか。
最近はネット上で本を買うんですけど、ときにはどうしても本屋に寄りたくて。それはネット上では出てこない自分にとってのおすすめの本と出会えるから。そういう未知との遭遇みたいなことがなくなっちゃうと、ちょっと寂しい気もしますけどね。
ドミニク:わかります。僕もまだ完全に理解してないんですけども、いわゆる人工知能系の研究の中で「サプライズ=驚きをいかに確率的に発生させるか」っていう研究があります。例えば、自動車の交通渋滞の研究で、交通事故という現象は数学的に非常にモデル化しにくいんです。
ただ、ビッグデータ研究のなかでサプライズモデルを考え出した数学者たちがいて、それを実際の交通状況に当てはめたところ、結構高い精度で交通事故も予測できるようになった。今度はそれを自分の好きな料理のレシピや本に転用しようという話がある。
菊池:同時にいつも思うのが、日本や国際的な話に持っていくと例えばGoogle検索した時の情報の紐付けの話って、そんなに単純ではないですよね。
「Diversity」という単語で画像検索した時、gooogle.comでやるのとgoogle.co.jpとgoogle.chでやった時では、全部違うものが出てくるんです。そういった情報の精査では、宮島達男が考える「Diversity」という言葉への紐付けは、今後そういう世界は見えているんですか?
ドミニク:見えていないとは思います。そこは技術者たちも試行錯誤でやっているところ。問題なのは、やっている人たちの動機が果たしてビジネスロジックで、資金源が一民間企業なのかどうかということも大きいと思います。さっき話したEuropeanaというEU全体でやっているアートアーカイブが研究者の中から熱い支持を受けていて、日本版Europeanaを立ち上げようっていう動きがあったりするんですよね。まずは東大の中でということで動きがあります。
宮島:絶対やるべきですよね。
『宝塔』に見る、アートの伝播
ドミニク:Europeanaがどうして生まれたのかというと、完全に「Google Books」に対する対抗策として、フランスとドイツがGoogleに激怒してはじめた計画なんですね。
宮島:世界中の美術館から、毎月のように「あなたの写真をウェブに載せたいから許可をください」っていう手紙が来るんですね。著作権を免除してくださいって。そんなのいちいち聞かなくていいよって言ってるんだけどさ。
ドミニク:あ、じゃあ…クリエイティブ・コモンズ・ライセンスでご自身の写真を公開しておけばバッチリですよ。
宮島:バッチリですか? そういうレベルにしたいんです。毎月来るからいちいちサインしてハンコ押して送らなくちゃいけない。それも毎年更新されるんだね、ああいうのって。馬鹿みたいだと思わない? 郵便料金が無駄だと思って。
ドミニク:連絡コストがかさみますよね。そういう時こそクリエイティブ・コモンズ・ライセンスですよ!
宮島:アートのリソースって、クリエイティブ・コモンズ化されるべきだと思ってるんですよね。
ドミニク:あえて違法か適法かを度外視して言うと、宮島さんの作品が著作権処理されていない写真がサイトで載っているのを見て、すごく感動して、そこに触発されて何か作り出している人たちもいるわけですよね。だから本質は法律であるとかビジネスではなくて、現象として創造の循環がドライブしているかどうか。
宮島:すごく面白かったのが、『宝塔』という作品があってミラー上にカウンター・ガジェットが乗っているんです。それをラスベガスで展示したんですけど、それがすごくヒットしていて。自分が映り込むんですよ。だから、自分が映り込んだ作品としてInstagramでアップするんですよ。
そうすると、そういうのを撮ったやつがバーッと出てきて結構面白いんですよね。ラスベガスのショッピングセンターみたいなところに設置されているんだけど、結構いい写真が撮られていて、買い物の途中のおじさんおばさんもいっぱいあって。Instagramで「hoto」って検索するといっぱい出てくるんだよね。