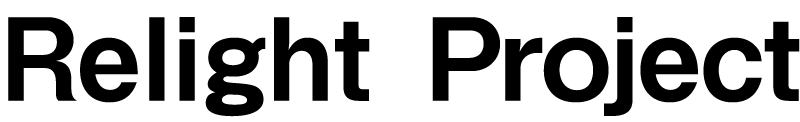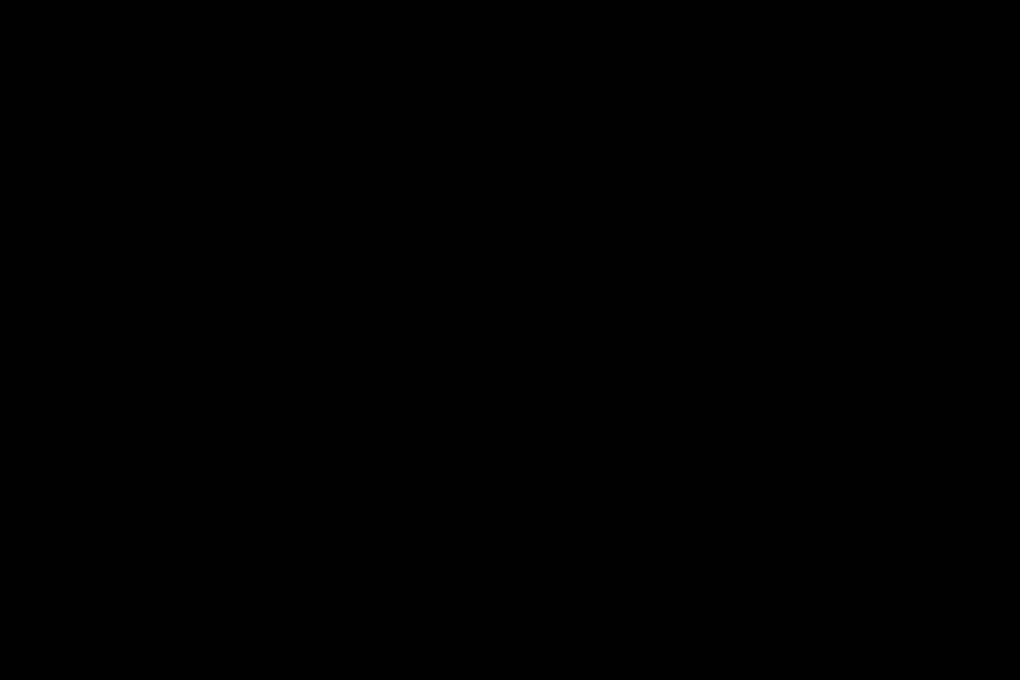社会の中で、自分の視点を持ち、主体となって動くことで その想いを形にする「社会彫刻家」。「生と死」というテーマについて、考えを深めた。
社会彫刻家という私×「生と死」この二つが重なりあう瞬間は、どんな時か。
ここに一片の詩がある。
『生と死の境にはなにがあるのだろう
たとえば国と国の境は 戦争中にタイとビルマの国境のジャングルを越した時に見たけれどそこには何もなかった
境界線など引いてなかった 赤道直下の海を通った時も標識ごとき特別なものは見られなかった 否そこには美しい濃紺の海があった
泰緬国境には美しい空があった スコールのあとその空には美しい虹がかかった
生死の境にも美しい虹のごときものがかかっているのではないか
たとえ私の周囲が そして私自身が 荒れ果てたジャングルだとしても』
(講談社文庫詩集「死の淵より」、高見順)
「生と死」とは、紙一重のように重なり合っているもので、境界線はなく、またその間には、何もないわけではなく、美しい虹と表現されるような美しい人のストーリーが存在するのみ。
生と死とは、ゼロかイチで定義できるものでなく、限りなく曖昧な概念なのかもしれない。
私は、仕事を通じて、その曖昧な概念の中で生きている多くの人に出会う機会を得ている。
聾話者の友人。 難病の子ども達を抱えるご家族。 死後の準備を始めたいというご老人。 この全ての人が、曖昧な生と死の間で、一生懸命に生きている。
みんなで撮った多くの写真が目の前に広がる。
写真に写る「私」は、耳が聞こえないわけでないし、難病の子どももいないし、病も患っていない。 曖昧な生と死の中で、明らかに「異質」な人間だった。
「傍観者」。
そこには共通して私という一人の傍観者が写っていた。
傍観者はネガティブな捕らえ方もできるが、傍観者だからこそ、境目の無い生と死の間で一生懸命に生きる人を“生”として認知し、応援できる立場になれる。
私は、リライトプロジェクトの成果として、難病の子ども達の支援になる「映画の上映会」を企画した。 この企画には、私の意志は存在しない、「傍観者」の提案である。
映画を見るという行為そのものは、薄い銀幕に隔てられた傍観者を産み出す行為に他ならない。 社会の中で人びとを支援する立場でいる時、傍観者だからできることがある。傍観者ができることについて、映画を見せるという行為を通じて、まずは多くの人びとに当事者になれない傍観者になってもらおうと思った。
という自分なりの考えを導き出せたのは、実はつい最近のこと。結果的に、映画上映の企画を考えたものの、実施までは至らなかった。例えば、傍観者に傍観者と認識させるしかけはどうするのか、どこで上映するのが適切なのか、本当に映画上映がベストな策なのか等々、企画としてアウトプットするには思考する時間を十分に確保することができなかったと反省する。
だからNo Actionという選択をする。
リライトプロジェクトを通じて、自分を「傍観者」という見方ができたことは、新しい発見があった。目に見える状態やモノは、何を意味しているのか。忙しい毎日の中でじっくりと考える時間はない。仕事の中では、成果を常に出し続けているものの、それ以外の場でアウトプットすることは少ない。そんな自分の今に気がついたときから、新しい始まりがあると思う。ここから自分のACTIONを起こしていきたい。